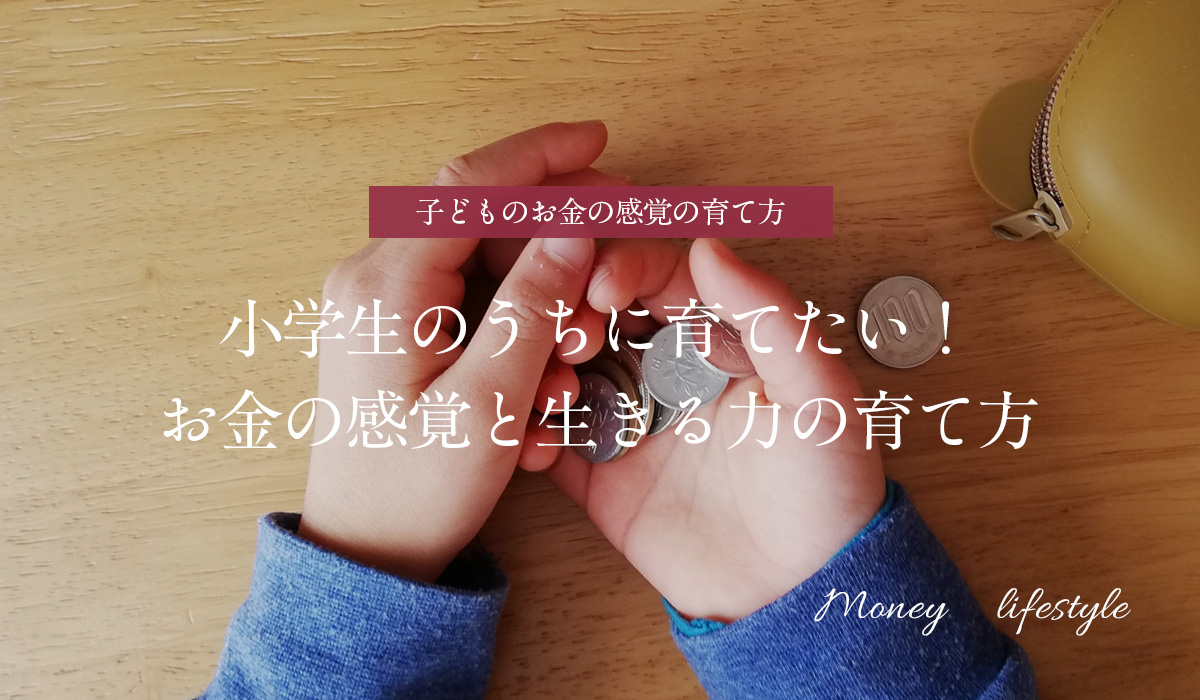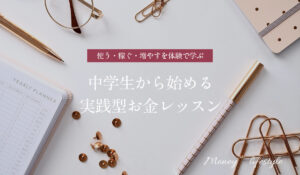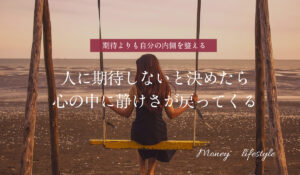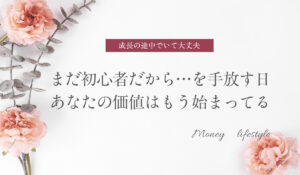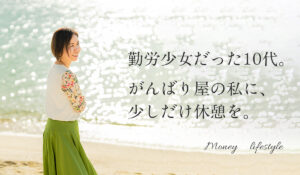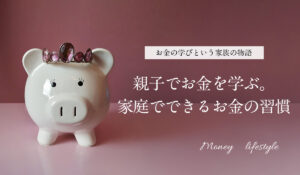SATSUKI
SATSUKIこんにちは!お金が残る経営の伴走パートナー
三原 さつきです。
「お金と心を整えて、自分らしく豊かに生きる人を増やしたい」
そんな想いで、日々サポートをしています。
「子どもにお金の話をするのは、まだ早いかな?」
そう感じる方も多いですよね。
でも実は、
お金の感覚は、読み書きや計算と同じくらい、早く育てていい力なんです。
お金の勉強=「お金持ちになるための話」ではなく、生きる力を育てるための学び。
今回は、小学生のうちからできるお金の感覚の育て方を、やさしくお話しします。
- 子どもにお金の感覚をどう伝えたらいいか悩んでいる親御さん
- 「お金の話はまだ早いかな?」と思いつつ、興味を持ち始めている方
- 小学生のうちに、子どもに生きる力や考える力を育てたい方
- おこづかいを通して、子どもに「選ぶ力」や「自己管理力」を身につけてほしい方
- 「使う」「貯める」「分ける」など、お金のバランス感覚を教えたい方
「お金教育」は金額よりも考え方から


まずは、お金=ありがとうの交換という感覚を伝えること。
たとえば、
- スーパーでお金を払うのは「ありがとう」のサイン
- 仕事をしてお金をもらうのは「誰かの役に立った証拠」
この考え方を知るだけで、
子どもたちは、もらうより与えるにフォーカスできるようになります。
つまり、お金の話を通して 「感謝と価値の循環」を学べるんです。
STEP①:おこづかいで「選ぶ力」を育てよう
お金教育の第一歩は、自分で考えて使う経験。
いきなり管理を教えるよりも、まずは「選ぶ自由」を与えることがポイントです。



例えばこんなこと!
- 欲しいものリストを一緒に作る
- 買ったあとの感想を話してみる
- 「また買いたい?」と聞いてみる
こうして体験を通して、「お金を使うとどう感じるか?」を体で覚えていきます。
ポイントは、失敗は大チャンス!
たとえムダづかいに見えても、「あのときの方がワクワクした」と気づく経験こそが宝物。
STEP②:「貯める」「使う」「分ける」の3分法を実践!


おこづかいの使い方を、3つの箱に分けてみましょう。
| 使い道 | 目的 | 目安 |
| 使う箱 | 自分の楽しみ・必要なものに使う | 50% |
| 貯める箱 | 将来や大きな買い物のために | 30% |
| 分ける箱 | プレゼントや寄付など誰かのために | 20% |
この、3分法を通して、
お金はただ「使うもの」ではなく、「育てて循環させるもの」だと自然に学べます。
STEP③:「体験」こそ最高の金融教育
親子でできる体験をどんどん取り入れましょう。
- スーパーで「今日の予算は1,000円チャレンジ」
- 一緒にフリマアプリで不用品を売ってみる
- おつりの計算をゲーム化してみる
お金の体験は、「正解を教える」よりも「一緒に考える」が大事。
親が先生ではなく、相棒になれる時間です。
おわりに:「お金の話」は生き方の話
お金の感覚を育てることは、
数字の教育ではなく、「自分を大切にする感覚」を育てること。
どう使うかは、どう生きたいか?とつながっています。
お金を「怖いもの」でも「すごいもの」でもなく、
信頼と循環のツールとして捉える子どもが増えたら、未来の社会はもっと優しく、豊かになるはず。
親も子も、一緒に育つマネーリテラシーの旅。
焦らず、笑いながら、今日から一歩ずつ始めてみましょう。